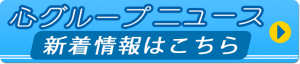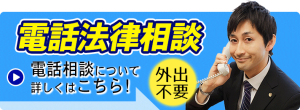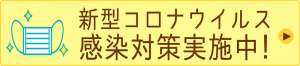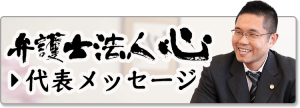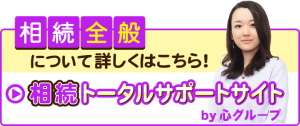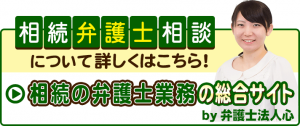相続放棄と管理義務
1 相続放棄の効果
相続放棄は、はじめから被相続人の相続人でなかったことになる、という効果があります。
この効果により、相続放棄済の元相続人は、被相続人の相続財産を一切取得することができなくなります。
被相続人の相続人でなくなる以上、原則としては、被相続人の財産とは一切無関係になります。
もっとも、例外的に、相続放棄後の元相続人には、相続財産の管理責任が残ります。
2 相続財産の管理責任
相続放棄をした元相続人は、次の相続人が相続財産の管理を始めることができるようになるまでの間、相続財産を管理しなければなりません。
次の順位の相続人がいない場合、相続財産管理人を選任するまでの間、やはり管理を続ける必要があります。
誰に対してどのような責任を負うかは、明文でもって具体的には定められてはいません。
法律上は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって管理をするということになっております。
善管注意義務よりは低い程度の注意義務ではありますが、相続財産の価値を減らしてしまわないようにする必要はあります。
不動産を放置しておくと、建物が倒壊したり、樹木が茂るなどして、他人に損害を与えてしまうことがあります。
そうすると、相続財産に起因した債務を負うことになりますので、これを避けるための行動を行うべきであるという考え方になります。
事実上も、建物が老朽化していたり、草が道路にはみ出していたりすると、市役所等から連絡が入り、対応せざるを得なくなるということもあります。
3 管理責任から解放されるためには
相続人全員が相続放棄をしている場合、最後に相続放棄をした元相続人には、相続放棄後も管理責任が残り続けてしまいます。
この管理責任を免れるためには、相続財産管理人の選任を行う必要があります。
相続財産管理人は、相続人不在となった相続財産を管理し、相続債権者がいる場合には返済等を行ったり、受遺者や別の相続人が見つかれば相続財産の引渡しを行うという業務を担います。
相続財産管理人が選任されれば、相続財産の管理責任は相続財産管理人に移行しますので、元相続人は管理責任から解放されます。
もっとも、相続財産管理人は家庭裁判所に対して、相続財産管理人選任申立てを行う必要があり、原則として数十万円から100万円程度の予納金を納めなければならないため、負担が少ないとは言えないのが現状です。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をしたら他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄はいつまで可能か
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄の効果
- 相続放棄をする場合被相続人の家にある物の管理はどうするか
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄と自己破産の違い
- 相続人全員が相続放棄をするとどうなるか
- 相続放棄を弁護士に依頼することのメリット
- 相続放棄の注意点
- 相続放棄の熟慮期間
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続放棄と法定単純承認
- 相続放棄の必要書類について
- 被相続人の保証人の方へ
- 生前の相続放棄
- 遺言がある場合の相続放棄
- 日本橋で相続放棄を検討されている方へ
- その他の地域情報
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒103-0028東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F
(旧表記:八重洲アメレックスビル6F)
(東京弁護士会所属)
0120-41-2403
お役立ちリンク